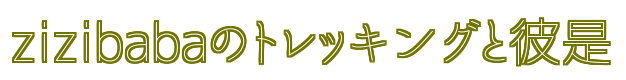人出は凄かったけどどちらも紅葉にはまだ早い様でした
そしてここ日光植物園は折に触れて立ち寄る場所で
四季の変化を感じ軽い散歩にもなるのでお気に入りの場所です
そこで今回はいつも園内から眺めていた憾満ヶ淵対岸に整然と並ぶお地蔵さんを
傍で見てみようという予定です
園の見学も終わり今一つ駐車場の場所がハッキリしなかったので
園の方に教わって10分位かな移動して見学して来ました

振り返ると園入口の先には冠雪した山が見える何処だろ?

紅葉も進んでいるようです

モミジガサ

左に見える建物は日本家屋を利用した休憩所です

もともとは幕末の会津藩主だった松平容保の居所として建てられたそうです

ロックガーデンにはダイモンジソウがたくさんありましたがほぼ終盤でした

リンドウはまだ現役





クサヤツデ


梅仁丹の様なムラサキシキブ

キッコウハグマ

オヤマボクチ


大正天皇記念碑傍の栗の大木
この木は大正天皇の御帽子掛の栗の木と呼ばれてるそうです


ヒナソウ



ミズバショウ池
この付近は旧御用邸エリアです

カキツバタ

ワスレナグサ



ミゾソバ

天皇をはじめとする皇族の方々が行き来した通御橋
2017年3月18年ぶりに新しく架け替えられたそうです

下を流れる田茂沢川では戦場ヶ原にに続きカワガラス君と再開(^-^)

ニリンソウが一輪

大池

憾満ヶ淵の展望台に降りてみます

勢いある流れと対岸の地蔵群
今日はこの後行ってみましょ

最後コナラの林を抜けたら駐車場です

憾満ヶ淵駐車場は先客10台といった駐車スペースです
(手前に大きな駐車場有り)
トイレも有って茶屋も有ります
茶屋は昭和前期~中期の戸建てアパート6棟の内一棟をリホームした感じで良い雰囲気です

参道に入ると直ぐに聖徳太子を祀った西町太子堂が鎮座しています

静まり返った森の中で石積みに囲まれた山門に趣を感じます

慈雲寺本堂
明治35年9月に洪水で流されてしまった本堂も昭和48年に復現されました

数万年前に男体山が噴火したときに流れ出た溶岩の滑らかな肌を急流が走る

いよいよ並び地蔵です
通称は化け地蔵ともいわれ行きと帰りに数えた数が違うそうです・・・ほんとかな?

昭和46年に輪王寺によって復元された霊庇閣
ここでは今は洪水によって流失しまったけど
対岸の不動明王石像に天下泰平を祈る護摩供養を行った護摩壇だそうです

対岸の台座であった巨石

カンマンという梵字が彫られている



もとは100体あったそうですが明治35年の洪水で大谷川が氾濫して
かなりの数のお地蔵様が流れてしまったようです
現在は復元安置されたもののようで所々台座のままのところが有りました



どんどん奥まで歩いてきたらこんな設備が有りました
古錆びた感じがここの雰囲気に溶け込んでいます

少し車道を歩いて憾満ヶ淵へ戻る途中で見かけたこのお墓は歴代住職のものだろうか?

戻ると先行して歩き始めていた外国のファミリーがまだ滞在中でした
みんなスタイル良くてモデルの様でお子さんもとても可愛かった

帰りに対岸の日光植物園から二本の小さな滝が流れ落ちている所へ降りてみました

素敵な表情で今日はおしまいです
☆
*****訪問ありがとうございました*****
また遊びに来てね(@^^)/~~~